日本建築学会構造委員会
著者:藤原 薫
1986年以降、東京湾岸や荒川流域などのウォーターフロントへ超高層建物を建設する計画が本格化し、軟弱地盤または液状化地盤における杭基礎の設計法を考える機会があった。それまで、地震力に対しては、建物の慣性力に対する許容応力度設計法しかなかったため、大地震時において発生する杭の応力を推定することは重要な課題であった。今も、その状況に変わりはない。
本論文では建物の慣性力と地盤震動の重ね合わせ法についてCQC法を基にした重み付け単純和を提案すると共に、既往の論文を分析している。重ね合わせ法についてはSRSS法で十分であるとの論文が多かったが、杭の二次設計法を確立するには代数和による重ね合わせ法でなければ発展性がないものと判断し、CQC法を基にした重み付け単純和にこだわり続けたわけである。
(以下、要約)
本論文では、「地下室は耐震性能上効果があるか」という問いについて、「地下室は杭への入力を常に減ずる効果があるか」という意味に捉えて整理してみた。この問題に答えるには、まず上部慣性力による杭応力と地盤変位によって生じる杭応力の重ね合わせを明らかにし、次に地下室の存在がどのように杭に作用するかを探ることになる。
本論文中の応力の重ね合わせ法に関する提案では、上部慣性力による杭応力と地盤変位によって生じる杭応力は静的に等価に重ね合わせて評価できるという立場に立っている。本来、上部慣性力に対する地盤の挙動は杭周辺地盤の局所的な性質であり、地盤震動における地盤の挙動は全体的な性質である。
したがって、地盤の局所的な性質と表層地盤の全体的な性質を矛盾なく静的に重ね合わせることは理論的に不可能である。しかし、応力の重ね合わせ法や地下部の設計用水平震度について厳密性を追い求め過ぎると、いつまでも大地震時に対応する終局強度型の設計法が確立できないという現実に突き当たってしまう。これでは上部構造の設計が既に終局強度型設計に移行している中で、基礎構造の設計だけが許容応力度設計法にとどまる現状を放任することになる。
兵庫県南部地震では杭に大きな被害が出たことは周知の事実である。一日も早く、現行の許容応力度型設計法を終局強度型設計法へ移行し、さらに上部慣性力だけでなく地盤変位の影響を杭の外力として取り込む必要がある。地盤変位の影響と地下部水平震度の設定法を暫定的に取り込み、杭の被害を少しでも軽減する設計法が実務の設計に供せられるようになることが望まれる。
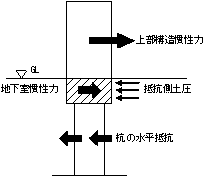 |
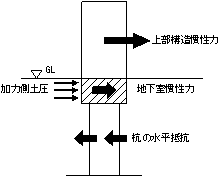 |
|
| 1)土圧が抵抗側に作用する釣合い系 | 2)土圧が加力側に作用する釣合い系 |
(補足)
大地震時において設計上、地下室の震度をどのように考えるかはいまだに明確にはなっていないが、本論文では地下室の設計震度は、上部構造の慣性力との同時性を考えると、おおまかにいって地表面加速度の0.5~0.6と考えれば概ね安全側であると述べている。つまり、1次設計に相当する地表面加速度80~100cm/s2の場合は0.04~0.05(現行の1次設計よりも小さな値である。)、2次設計に相当する地表面加速度400~500cm/s2の場合は、0.20~0.25とすればよいことになる。
しかし、地下室の等価な水平震度は上部構造物の慣性力と地下室の慣性力の同時性によって決定されるので、外見上同じ建物の形をしていても従来の耐震建物と免震建物では異なるのが自然である。当然、免震建物の方が大きな水平震度をとらなければならないことは理解できよう。具体的に計算したい場合には、本論文を参考にするとよい。







